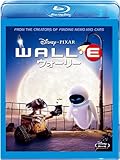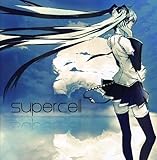ミュージカル「キャッツ」, Twitter、始めました, きょうのつぶやき
ミュージカル「キャッツ」, Twitter、始めました, きょうのつぶやき
ミュージカル「キャッツ」
ご存じ、日本では劇団四季がもう25年間もロングラン上演しているミュージカルです。
もう20年くらい前、僕の妹がまだ小学生くらいだった頃1、彼女がとてもはまっていたことがあって、その時に歌を一緒によく聴いていました2。
それ以来、「いつか生で見たいなぁ」と思いつつこれまでは機会が無かったのですが、いよいよ千秋楽が近い、と言う報道や3、子供料金が割引になったり(^^;していたことが後押しとなって、えいやっ、とやっと今年一月に行ってみることにしたのでした4。
さて当日、五反田のキャッツシアターへ入り、猫たちの写真が飾られたホワイエを抜け、いざ劇場に入ってみてびっくり。「キャッツシアター」がああいう劇場だとは実際に行くまで知らなかったよ。
どんな劇場かというと、劇場全体が、猫たちの住む、人の来ない、ゴミだらけの、いかにも猫たちが夜の集会をしていそうな広場を模して作られているのですね。劇場に入ると観客も猫スケールになるという設定なので、とても巨大な自転車やギター(のゴミ)が所狭しと壁や天井に置かれていたりします。
そして中央には回転式のステージ。今回、ちょっと早く行きすぎてしまったんですが、劇場の中にあるものを子供たちと指をさしては「あ、あんなところにギターが」とか「超大きいやかんがあるよ!」などと見て回っているだけで、あっという間に開演となりました。
ところで、僕は学生時代、演劇部の人たちとも交流があったこともあって5、当時は時々、いわゆる小劇場に公演を見に行ったりしていたこともありました。今回劇団四季の公演を初めて見るにあたって、当時のアマチュア小劇団の演劇とは、きっと全然違うのだろうな、と思っていました。
ところが、予想は良いほうに裏切られました。四季のような大規模で商業ベースな劇団でも、演劇は演劇なのですね(「キャッツ」はミュージカルですけど・笑)。観客との距離の近さや劇場全体を使った演出など、久しぶりに味わう演劇の世界はとても素晴らしかった。
今回、子供たち+あゆみさんは予備知識0で行ったんですが、思いのほか楽しめたようでした。intermission 中、劇場に入るときはささっと通り過ぎただけだったホワイエの写真たちを、「見たい!」と言って見に行ったり(中でもラム・タム・タガーが一番人気)、帰り道では早速今聞いたばかりの歌を歌っていたり。家に帰ってから、お父さんは早速キャッツのサントラを買ったりしたんですが6、有葉などはずいぶん聞き込んでいるようでした。
なお、今回ちょっと失敗だったのは、予約するときに座席をブロックの中心付近にしてしまったことと7、夜の部に電車で行ったこと。公演が終わったのが9時前で、それから夕飯を食べてから電車で帰ってくると、最寄り駅に着いたのはもう11時過ぎ。いつもは9時には寝ている鳥乃などはさすがに辛そうで、ちょっとかわいそうでした。
Twitter、始めました
ひびきさんにお誘いを受けて、遅ればせながら Twitter を始めることにしてみました。ユーザ ID は何のひねりもなく、「digitune」です。よしなによしなに〜。
ちなみにアドエスからの更新・閲覧をどうしようか悩んだんですが(ケータイから更新できないと意味ない感じですもんね)、ACCESS の NetFront Widgets を使ってみることにしました。今のところなかなかよさそうな感じ。
きょうのつぶやき
仕事中。 (12:18 webから)
男女比の極端に偏った職場×非自社ビル=トイレ難民発生(汗 (17:57 webから)
右上の数字は書ける文字数なのか (18:08 webから)
ようやくアドエスからも見られるようになった… (20:57 webから)
今日は月が見えないや (21:32 webから)
ぷはー風呂上りの一杯は格別だ!(ただし水道水) (22:39 webから)