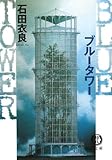きょうのつぶやき
きょうのつぶやき
きょうのつぶやき
日本人が飽きやすいのは、人より早く「飽きた」というのがカッコいい、みたいな風潮があるからかな?<と分かったようなことを書いてみる。 (08:22 webから)
僕は飽きやすい人をカッコいいとは思わないけどねー。仕事でも遊びでも、コツコツずっと続けられる人にリスペクトするっす。 (08:24 webから)
そういや先週、僕の実家に顔を見せに行ったら「お中元のメロンをゆうパックで送った」と言ってたのだけれど、未だ届かず。正常化宣言出てなかったっけ。熟しすぎてグチャグチャになったメロンは厳しいにゃあ! (08:32 webから)
androidの、アプリ利用中→通知到着→通知欄引き下げ→アプリ切り替え(例えばtweeter)→戻るボタン一発で元アプリへ復帰、の流れが秀逸過ぎる。しかもネスト可。iPadでいちいちhomeに戻らないといけないのがすごい苦痛なんですよね…。 (13:47 twiccaから)
tweeterってなんだww。twitter or tweetと読み替えておくんなまし。 (13:49 twiccaから)
前にも少し書いたけど、確かにタッチ主体で操作しているときに物理キーを押さないといけなくなると、その要求されるトルクの差に一瞬戸惑い、ストレスに感じることはあるな。 (20:30 twiccaから)
触れば良いタッチに対して、物理キーはとても「重い」んだよね。フツーのケータイのキーと比べてxperiaのキーが特別重いわけじゃないんだけど、落差が辛い。 (20:33 twiccaから)