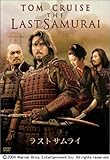「アウトブリード」, 「ラスト・サムライ」
「アウトブリード」, 「ラスト・サムライ」
「アウトブリード」
 これまで、何冊か保坂さんの本を読んできましたが1、小説以外の本を読むのは初めてでした。この本は保坂さんがいろいろなところに発表した書評や、友人との書簡、その他を集めた「エッセイ集」ということになっています。
これまで、何冊か保坂さんの本を読んできましたが1、小説以外の本を読むのは初めてでした。この本は保坂さんがいろいろなところに発表した書評や、友人との書簡、その他を集めた「エッセイ集」ということになっています。
保坂さんの小説は、たいてい保坂さんを連想させる小説家が主人公だったり、登場人物が本当にいそうな人ばかりだったりして2、僕はてっきり、保坂さん自身が小説の登場人物のような人で、日常の思考の延長線上で小説を書いているんだと、つまり彼自身と小説の主人公はかなり近い人物なのだと思い込んでいました。
確かに、彼が日頃考えていることを小説として書いていることは間違いないのですが、しかし彼は無自覚に自分の流儀で話を紡いでいるのではなく、とても自覚的に、小説として登場人物たちにいろいろなことを考えたり話させたりしているのだと、この本を読んで初めて知りました。
ところで、「カンバセイション・ピース」でも「愛っていうのは、(中略) 偶然が絶対化することなんだよ」なんてセリフがありましたが、この本 (「アウトブリード」) でもとても重要な人として描かれている「樫村晴香」という哲学者の人が、保坂さんの中学生の時の同級生だ、という後書きを読んで、なんだかすごく首尾一貫した感じを受けました。
僕達はなんとなく、偉大な哲学者や小説家が僕等とは比較にならないような情報源や人脈を持っているかのように、そうでなくてはあれほど普遍的に価値を持つ文章を書くことが出来ないかのように考えてしまいがちですが3、全然そんなのは間違いだった。保坂さんの文章に普遍性を感じるなら、それは実は単純に彼が人間であるがゆえに生み出し得る普遍性なのだなぁと。
そういえば保坂さんもカントの「純粋理性批判」を読んで途中で興味を失っている、と書かれていてちょっと面白かった。その理由というのが、「カントがア・プリオリだと言っていることに納得できなかった」から、だそうなんですけれども、僕もちょうど同じことを「プロレゴメナ」を読んでいる時に感じたのですね。「プロレゴメナ」を半分読んだところでの僕なりの理解で言うと、カントが「ア・プリオリ」だと書いていることは、どうも身体的な認識の形式のことのようなんですね。人間の身体的構造に伴う感覚信号のフォーマット、というか。カントの時代にはそれってほとんど絶対的なものだったのかもしれませんが、さまざまな道具で感覚や認識を拡大しつづけている現在に生きる僕等にとって、感覚信号のフォーマットが世界認識に対してそれほど絶対的なものだとは思えなくなっていると思ったのです。
それにしてもいつものことながら、本屋の店長のお薦めはとても適切だなぁ。確かに、保坂さんの感性には近しいものを感じるというか、すごく共感する部分があります。
「ラスト・サムライ」
それで感想ですが、うーん、それなりには面白かったけど、僕的には「激萌え」というほどではなかったなぁ。SAK は群集合戦シーンが大好きなんだよね。「トロイ」も絶賛していたし。
僕があんまり楽しめなかった理由は、(僕が日本人のせいか) 風景の描写があまりに嘘臭く感じてしまったことかな。勝元の村もなんだか LOTR のホビット庄みたいだし、横浜の街のスケール感も変。合戦シーンもまるでゴルフ場で戦っているようで、あんまり「日本」らしくなかったと思う。その辺の違和感が最後まで引っかかってのめり込めなかった、ってところかなぁ…。
しかーし!来週のデカレンジャーはどうもこの「ラスト・サムライ」のパロディの予感!そういう意味でこのタイミングで予習させてくれた SAK には深く感謝しておりまする。どーもありがとう!
コメント
- SAK (Fri, 11 Jun 2004 01:40:15)
-
ショー・コスギのニンジャ映画を喜んで見ていた私に言わせると、
「ハリウッドもココまで日本を知っているとはっ!」と思える衝撃の
正確さなのだが>ラスト・サムライ。
霧の中から浮かび上がってくる鎧武者たちのシーンで、もうこの映画ははオッケーでしょう。撮影場所がアメリカのため、日本にはない木が生えてるのはご愛敬。
なんで日本の時代劇は、あーゆーシーンが撮れないのかと……ブツブツ
横浜シーンは、私はとんでもないリアルさと思った。
「映像の世紀11 JAPAN」で見た当時の記録映像にすごく近い。
明治初期の日本の風景は、想像以上にヘンです。はい。
あとは、所詮セットなんだから細かい事でガタガタ言わない。
え〜、群衆戦大好きな私の次のターゲットは、「アラモ」http://alamo.movies.go.com/main.html ですな。
米義勇兵187人vsメキシコ軍7000人の13日間の泥沼の戦い。
アメリカ愛国心ヽ(´ー`)ノマンセーな大バカストーリーにも期待。制作ディズニーだし。
ただ、アメリカで大コケしたらしく、日本で公開されるのか微妙なのが(;´Д`)
- SAK (Fri, 11 Jun 2004 01:59:40)
-
>勝元の村もなんだか LOTR のホビット庄
どっちも撮影ニュージーランドなんだから、似てて当然な気もするが。
ちなみに、最後の合戦シーンは「ラグビー場」と言われております(笑)
考えてみると、我々が見慣れてる日本の山林って、杉とかが植林されまくった
人工の林ばっかりで、江戸末期〜明治初期にあった、天然の照葉樹林の風景って
よく知らないんだよね。
仮に、当時の日本の風景を何らかの方法で正確に再現したとしても、見慣れてない
せいで、やっぱり違和感を覚えると思われ。
- ねおん (Fri, 11 Jun 2004 09:41:12)
-
> 俺だけ?(笑。
少なくともワシはちがうw
だいたい人物観察やら体験やら調査したことやらなんにしても、最終的に自分に着地したものでないと、他人に説得力などもたん。「私の中のあなた」をどれだけ持てるか、とゆーのが大事じゃな。
ところで「季節の記憶」、半分まで読んだので途中感想じゃ。この雰囲気や文体は割と好き〜。みょーにクールなとこもよいな。あえて言えば大江健三郎っぽいかも知れん。理知を感じて、ツネ好みなのは、なっとくじゃ!
ただの〜、ワシが好きになるには、もうちょいひっかかりがないとの〜。あまりにまったりしすぎじゃてw
あと半分読むとまた違うかも知れんので、途中感想終わりじゃ。
- ねおん (Fri, 11 Jun 2004 09:47:06)
-
終わりな侍を観て。。。「七人の侍」はほんと偉大じゃな!まだ観てない諸兄はぜひ見ませう。アホなハリウッド映画、束でかかっても勝てん映画じゃ。
- ねおん (Fri, 11 Jun 2004 09:47:51)
-
だがワシは「用心棒」のほーがもっと好きw
- Digitune (Fri, 11 Jun 2004 21:56:54)
-
> 横浜シーンは、私はとんでもないリアルさと思った
ディテールのリアルさはあるんだろうけど、俺的に違和感があったのはスケール感なんだな。
なんだかケチくさい路地のようにしか見えんかった。あんなところに勝元やオルドリンさん
が来るとは思えん。
> 所詮セットなんだから細かい事でガタガタ言わない。
ほーい。
> どっちも撮影ニュージーランドなんだから、似てて当然な気もするが。
「似てる」ことが問題なんじゃなくて、日本らしくないような気がするってこと。ああいう風に
木のない丘っぽい地形がそもそもあんまりなさそうだし、丘の上に家を立てたりはあんまり
しないんじゃなかろうか。
> 考えてみると、我々が見慣れてる日本の山林って、杉とかが植林されまくった
> 人工の林ばっかりで、江戸末期〜明治初期にあった、天然の照葉樹林の風景って
> よく知らないんだよね。
SAK の地元なら俺等が小さいくらいのころならかなり自然の状態が残ってたんじゃないの?
僕等が小学生くらいの八王子でも結構自然っぽい山が残っていたように思うが…。
http://www.yomiuri.co.jp/tabi/yama/tokyo04_meiji.htm
↑ここによると自然林と人工林との調和が…とか書かれてますな。
- Digitune (Fri, 11 Jun 2004 22:29:13)
-
> 少なくともワシはちがうw
あはは。そうですか。どうも僕は「すごい!」と思った人が自分と同じ人間だ、ってことを信じてないようなところがあります(笑。保坂さん流に言うと、僕もそういう人達を「拒絶」してるのかなぁ。
> ただの〜、ワシが好きになるには、もうちょいひっかかりがないとの〜。あまりにまったりしすぎじゃてw
むむむ。そうなるとたぶん最後までひっかかりはないんじゃないかと思います。ちょっとネタばれかもしれないけど、「アウトブリード」から引用すると、
「『季節の記憶』でやってみようと思ったことは、(1)風景を、人間の心の投射とか比喩とか象徴のような"文学的な意味"を持ったものとしてでなくて、ひたすら即物的に風景として書くことと、(2)ぼくが世界や人間について考えていることを出来るだけたくさん書き込んでいくことの二つだった。」
なんて保坂さん自身が書かれていますから。人の生活におけるイベント的な意味では、保坂さんの小説はどこまでいっても「まったり」です。
彼の、このある種特異な形態の小説は、例えば次のような認識などに源があるような。同じく「アウトブリード」からの引用ですが (直接読んじゃった方が早いかも…)、
「小説にはどうして細部が必要なのか僕はずっとわからなかった。
作品に何か一つ明確なテーマがあるのなら、数学の証明問題のように必要なことだけ書き連ねていって最後に、Q.E.D.(以上証明終了) とだけ書けばいいじゃないか。それなのにどうして小説は、朝起きたときの光の様子や、(中略) 道で出会った女性の髪が長くてその髪が風になびいたことなんかを書いていく必要があるのか、僕には本当に理由がわからなかった。ただ、いままで書かれてきた小説がそうだから、いま書かれている小説もそうで、これから書かれるだろう小説もそれを踏襲するのだろうとしか思えなかった。田中小実昌の『ポロポロ』に出会うまで。
(中略)
『ポロポロ』にはさきの疑問についての答えが剥き出しになっていた。
小説というのは書こうとする中身を書き手の生理をともなって書いていくものだったのだ。」
彼のこういう言明を見ると、僕はすごく納得してしまいます。
- Digitune (Fri, 11 Jun 2004 22:33:13)
-
そういや黒沢映画は一回も見たことがありません。どこかで一度は見ておかなくちゃ。
// 保坂さんのお話を読んでいると小津安二郎さんの映画も見たくなります。
- ねおん (Sat, 12 Jun 2004 09:59:41)
-
うむ、最後まで読んだが、やはりまったりじゃったなw
ツネが引用しているところどおり、こういう小説は、読み手と生理的なものが合えば、それだけで価値を持つのじゃ。ある意味音楽的なんじゃな。
- ねおん (Sat, 12 Jun 2004 10:04:38)
-
小津安二郎の映画は、気に入るかも知れん。ストーリーそのものは、ある雰囲気を描き出すための設定にすぎない、とゆー感じじゃ。保坂さんはかなり好きそうじゃの。とりあえず「東京物語」からおすすめじゃ!
小津といえば、低い畳座位からのカメラ目線にも注目じゃ。おっとスノビズムじゃのおw
- Digitune (Sun, 13 Jun 2004 09:24:16)
-
> ある意味音楽的なんじゃな。
うーん。この言葉にはちょっと驚きました。僕はこれまで保坂さんの小説を読んでそういう風に思ったことはなかったんですが、言われてみれば確かにそういう感じ…。「アウトブリード」を読む限り、保坂さん自身の指向とも一致するように思います。
いろいろありがとうございます>ねおんさん。